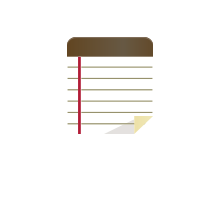さいきん私は、よく「かみさまに手紙」を書く。
いや、もはや「手紙」と呼べるほど可愛いものではない。
そこには、つらつらと「暴言」とも言えるような、
または「無茶な要求」とも呼べるような言葉達がチカラ強く並べられている。
かみさま、に手紙を書く時は遠慮をしない。
だって、かみさまは私たちのことをいつも見守り、
そして一番に思ってくれているのだから。
だから、文句を言う。
そして、時には涙や鼻水を垂らしながら
自分の雄叫びを浴びせるのである。
—
かみさまに手紙を書こうと思ったのは、
わたしがとある出来事をきっかけに、
辛くて辛くて辛くてどうしようもなかった時があったからだ。
辛くて、辛くて。
でも、
こんなことを仕事にしているし、
自分のその辛さが、誰かや何かのせいではなく
「自分の捉え方」であることくらい、
重々に承知だった。
でも。
その事実さえもが絶えられなかった。
この仕事をしていることさえ恨んだ。
どうして「理解」しているのだろう。
どうして「わかって」しまっているのだろう…と。
そうやって、わたしの辛さに、
自分の「本当の原因」を知っているからこその二重の苦しみが加わったのである。
—
だから手紙を書いた。
「かみさま、私は知っています。」からはじまり。
何に対してどういう風に見えていて。
多分それは私の中にある「思い込み」だし、「価値観」だし、
それは私次第でなんともなると知っていることを前置きにして。
暴言を吐いた。
「でも、どうして?」って嘆いたんだ。
—
確かに、こういうことをずっとやっていると、
もはや誰も責めることが出来ないとわかってくる。
最後の矛先が自分に向けられてしまうことさえ、
心が痛んでしまう。
「そうなの、愛さなければいけないのよ、自分も他人も…」
と、どっかで何かを覚えた自分が耳元でそう囁くんだ。
ただ、時にはそれに対して
真っ向から反対したい!と思うことがある。
何もかもを無視して、
ただ子どものように「いや!」と言い、
そして自分のすべてをぶつける。
そう、暴言を吐いているのではなく、
かみさまに「私自身をまるごとぶつけているんだ」
と気付いたのは、そのずいぶん後だったけど。
でも、たいそう気持ちのよいことだった。
これほど気持ちいいものなのか!と思い
その後かみさまに感謝の手紙を書いたほど・・・。
それからと言うものの、
気付いたときには、かみさまと文通するようになった。
—
文通、とは言え、家のポストに返信があるわけではない。
かみさまは、「現実」で手紙のお返事をくれること、
知っていたから手紙を書いたあとは
いつもより慎重に、現実に耳を傾ける。
わたしの声、聞こえました?
あれが嫌だ、って言いましたよ。
ちゃんとお願いしますね、かみさま。
って。
そうやって、いつもの日常に
お返事のカケラを感じてみようとするの。
なんだか、そうやってしていると
きっとどこかで私を、よしよししてくれようと企んでいる気もして
いつも頑張っているの、知っているでしょ?
わたし、そんなに強くないんだからね、と言った言葉も
ちゃんと聞いてくれている気がして。
なんだか、いつもより
優しい気持ちになれたりする。
お、すごい、かみさま。さっそくギフト!
でも、嫌なもんは嫌だからねーと。
今日もまた、そうやって上のほうに言ってみる。
—